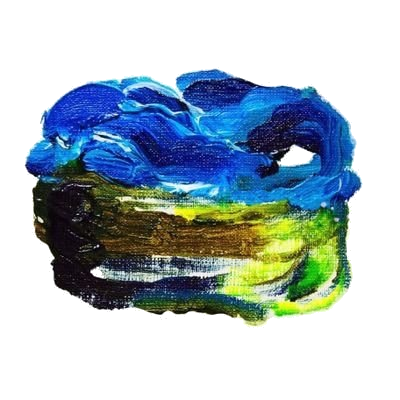私、あおいうには「夢や幻触」「カルト2世」「女性性の開放」といったモチーフを通して、トラウマや日常でふと感じる違和感などを絵画に置き換える、個人史の視覚化を試みている。表現の根底には、制度的に見過ごされがちな社会的弱者の感覚や立場を含んでおり、いわゆるポリティカル・コレクトネス(PC)では捉えきれない領域を内包している。
美術の歴史的には、表現主義や日本の表現主義→抽象表現主義→新表現主義の系譜、シュルレアリスムにおけるオートマティズム、社会彫刻、パフォーマンス・アート、フェミニズム・アート、宗教画などの様々な文脈を引用しており、また、新たに「メンヘラ・アート」を現代美術に輸入するという画策もしている。
作品を公にする行為は、自らの痛覚(触覚)を外界へと曝け出す行為だ。
鑑賞者が自らの記憶や体験と作品とを重ねることで、内在する感情が可視化される。
私の絵画は治療のためのものではない。しかし、言葉にならないトラウマを再演することで、傷が居場所を得る。世界との再接続の契機を果たすだろう。それは、身体性の奪還や経験の政治化にも接続されうる。
制作を通して幾度もトラウマを反復し、少しずつ越えていく。その連続性こそ美術の価値だと確信している。